メンバーの紹介で、テューバ奏者の初めての見学者さんに来ていただけました
そして即日!入団いただくことになりました!!

その日に渡した楽譜ですぐに合奏に入っていただきましたが、素晴らしい演奏をされる方でした
豊かな音色なのですが、良い意味での明瞭さ(クリアさ)もある音で、引きずるような重々しさがありません
楽に演奏しているように見えるのに存在感のあるサウンドで、もっと広い部屋で聴いてみたいくらいです

テューバ奏者が2人になってサウンドに広がりと深みが増して、聴き惚れてしまいます
こんなに誉め殺しにすると、もはや嫌がらせ??
あ〜気候もいいし、5月ってサイコー
と、チョーごきげんな日になりました
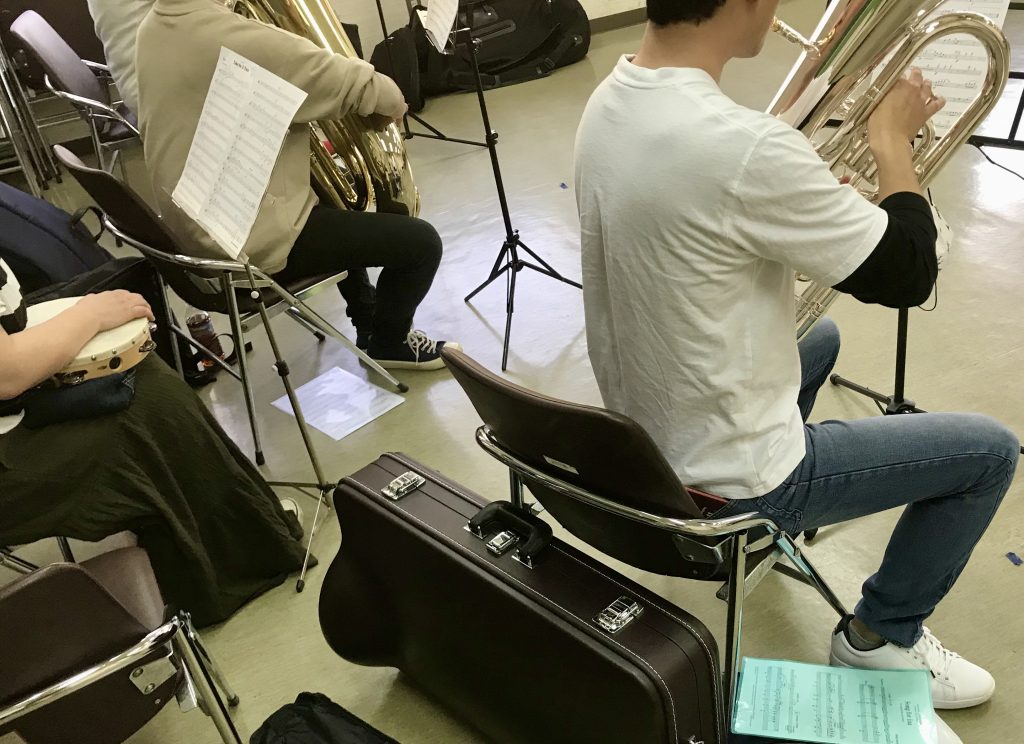
そして一緒に来ていただいたご家族の方に、急遽タンバリンで合奏に入ってもらうというムチャぶり
ところがリズム感と勘の良い方で、すんなり全体に溶け込んでました
打楽器の経験がないとは思えないくらいです
おっと「A列車で行こう」の発車オーライ、初合奏だったことを忘れてました
ジャズを一年中やっているわけではないので、吹奏楽でたまにスウィングが出てくると、苦手な人は多いです

音符の価値が変わってくるので(普通、八分音符は四分音符の半分の長さ、ってのが通用しない!)、音符や休符の長さを数学的に捉えてると、
「あれ〜???」となってしまいます
大学のビッグバンドやジャズサークルのように、ずーっとジャズばっかりやっていれば、だんだんと慣れてくるのですが、そうすると今度は逆にクラシック的な演奏が上手くできなくなってしまいます

音楽をジャンル分けすることにあんまり意味はない、と以前に書きましたが、演奏する身になると実は思った以上にジャズとクラシックの間には「大きな壁」があります
ジャズトランペット奏者のウィントン・マルサリスは、クラシック演奏のレコーディングでグラミー賞を獲ったこともありますが、それぞれの間は結構日数を空けて準備しないと上手く演奏できない、と言っていました
つまりクラシックとジャズを同時期に演奏することはないのです

吹奏楽では一つのコンサートの中でクラシックとジャズやポップスをやるのはごく普通のことですが、実はかなり高度なことをやっているとも言えます
野球部の人がサッカーを高レベルでをやるようなもの、いや、茶道部の人がラグビーをやるくらい、(同じ楽器を使うけれども)種類の違うものと言っていいと思います
日本のプロの吹奏楽団はポップスやジャズの演奏やレコーディングをすることもよくありますが、やはりクラシック畑で勉強してきた方々なので、特にジャズはあまり上手くありません

自分の好きなジャズの演奏家を見つけて、たくさん聴くことがジャズを上手く演奏する近道なのかもしれません
慣れ親しむのが一番です
こどもの頃、トムとジェリー(アメリカのアニメ)が大好きで毎日のように見てましたが、ジャズやクラシックがしょっちゅう音楽として使われてました
「ジャズ奏者の音色がどうも受け入れられない」
と思われる方も多いです
確かに美しい音色を重視するクラシック奏者に比べると、ジャズ奏者の音色が「汚く」聴こえてしまう気持ちもわかります
特に最近は押しの強いパワー系の奏者じゃないと評価が得られない風潮があるようにも思えます
1960年代くらいは繊細な演奏をするジャズ奏者が今よりは多くいたので、過去の演奏家から好みのプレイヤーを探すのもいいかな、と思います
無理矢理「ジャズの感覚を勉強しよう」とか思って聴くよりは、なんとなく気に入ったのを繰り返し聴いていく、方がいい気がします

新しく入団していただいたテューバ奏者の方の楽器は「C管(ツェーかん)」でした
テューバはB管、C管、Es管、F管、とその時々や奏者の好みによって、使う楽器の調性が様々です
と言っても初めてテューバを演奏する人は、ほとんどB管(ベーかん)の楽器で始めます
自分の楽器(テューバ)を買う!
となった時に、以前はB管をまずは選ぶことがほとんどでしたが、最近は初めて買う楽器がC管というテューバ奏者も増えてきたようです

「B管とかC管とか、何が違うの?」
と思う方は多いです
「どの楽器もC管にしたら、移調とか面倒臭くなくていいのに」
「ドがシのフラットとか、意味わからん」
と言われることもあります
ごもっともなのですが、楽器職人さんが何十年、何百年と楽器を作ったり改良してきた現在でも、そう簡単にはいかないのが現状です

楽器職人さんは、当然どの楽器でも「C管」を試しに作ってきたはずです
いろいろと試してみて、結果「B管」がもっとも総合的に優れていたので、多くの楽器でB管が今でも主流になっています
吹きやすさ、音色の良さ、音量、イントネーション(音程)の正確さ、楽器の製作しやすさなど、他にもいろんなことを含めると、C管は少し長所短所のバランスが良くないのです(B管より優れている点もあります)

管楽器はどの楽器でも100年前とほとんど同じシステム、ほとんど進化してないと言えますが、それでも少しずつ製作技術は上がってきました
コンピュータなどが導入されて、人間の勘に頼ってきた部分がより正確に、短時間で効率よく製作できるようになってきた点が大きいように思えます

C管の短所の一つである、イントネーション(音程)の悪さも、少しずつ改良されてきて、以前よりは随分と扱いやすい楽器が多くなってきました
「イントネーション(音程)が悪い」というのは、例えば「ド」に合わせると「ミ」が低くて「ソ」が高い、というようなことです
ちなみに「ピッチ」も音程のことですが、
「この楽器はチューニング管を全部入れてもピッチ(音程)が低い」
という風な使い方をされます
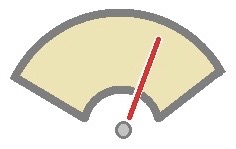
「ピッチ」と「イントネーション」の区別がついてない人は多いです
どちらも日本語で言えば「音程」、しいて言えば
「ピッチ(絶対音程)」
「イントネーション(相対音程)」
と言えば分かりやすいでしょうか
「イントネーション」を、音の立ち上がりのことだと勘違いしてる人も多いです
音の立ち上がりは「アタック」です
管楽器の場合「アタック」と「タンギング」という言葉は、同じように使われることが多いです

吹奏楽コンクールの審査員も、講評に「ピッチが合ってない」とか書く人が多いですが、チューニングが合ってないと言うよりは、個別の音が合ってないことの方が多いので、
本来は「イントネーションが合ってない」と書くべきです
文字数が多いからか「ピッチ」という言葉の方が多用されてますが、それなら「音程が合ってない」と書けばいいのに、と思います
話がそれてしまった!
テューバやトランペットは、特にオーケストラではC管の楽器が使われることがよくあります

C管はイントネーション(音程)の癖や、下手すると痩せた音色になりやすいこと、などを奏者の技量でカバーできれば、場合によってはB管よりも使い良い楽器になりえます
なので「C管は上級者向きの楽器」と言ってもいいと思います
曲やフレーズによっては「運指がやりやすい(やりにくい)」というようなメリット(デメリット)も、時々あります
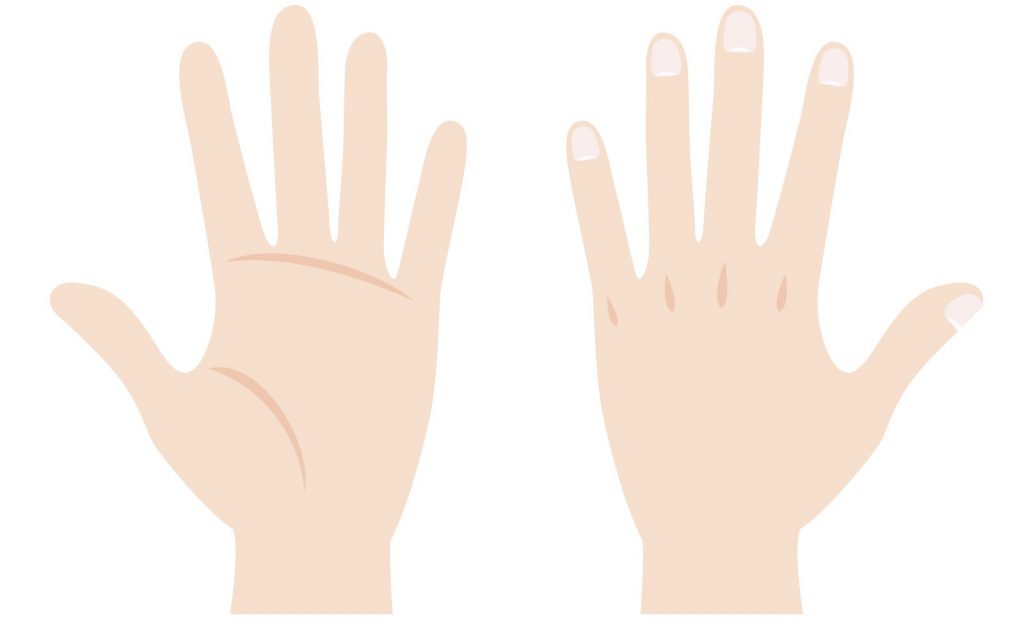
C管のテューバは特に、ぼんやりした音にならず、適度に音が「立つ」ことで、大編成の中での聴き取りやすさなども含めて、上手く演奏できれば「万能な(ちょうど良い)」楽器に思えます
「たっぷりとした豊かな音色」とかに限って言えば、B管の方に軍配が上がります
C管は音のスイートスポット(おいしい部分)が狭いので、ちゃんと頭の中でその音を歌えてないと、痩せた「ポヘ〜」という感じの音になりがちです
B管は楽器としての懐が深くて、なんとなく息を「ぼんっ」って入れても、まあまあ良い音が出てくれます

トランペットのC管は、B管とそんなに変わらないかと思いきやけっこう扱いづらくて、中高生くらいの経験では上手く吹きこなせないことがほとんどです
初めてC管を吹いた時は「吹きにくー」と思いました
しっかりとした奏法、柔軟性、基礎的な力量、良い耳を持ってないと、音色も音程も使い物になりません

逆に良い音や正確な音程を聴き分けられる耳と、しっかりとした奏法が身に付いていれば楽に響かせることができるので「B管たまに吹くとしんどい」と思うほどになります
どんな調性の楽譜でも、サッと移調(トランス)できるスキルも必要になってきます
オーケストラ曲のトランペットパートは、1曲の中でも楽譜に「in B」「in A」「in F」「in E」など、しょっちゅうKey(調性)が変化して記譜されている曲がたくさんあります(それがどうして?かはまた別の機会に)
トランペットのC管が、B管に比べると現在でも吹きにくい楽器が多かったりするのは、製作過程で短い管の中での精度を出すのが難しい点もあると思います

金管楽器の「マウスパイプ」は、どの楽器でも少しずつだんだん太くなっていきます
その加減が均等で精密に作られていると、イントネーション(音程)の癖が少なくなります
マウスパイプの作りが雑だと、逆に大クセ使いにくい楽器になってしまうのです
凹ませたりしないように気をつけましょう

もちろん楽器の良し悪しはマウスパイプだけでは決まりませんが、マウスパイプはかなり重要な箇所です
マウスパイプだけを専門で研究、開発、製作している楽器職人さんやメーカーもあるくらいです
21世紀になって、精度は上がってきたけど、なんかどうも魅力に欠ける楽器、というのも増えてきたように思えます
オートメーション化されて、ハンドメイド色が薄くなってきたことによる弊害でしょうか
楽器作りや良い楽器選びは、本当に難しいと思います

また楽器の話ばっかりになってしまった
テューバ奏者が2人になったので「春の祭典」「ツァラトゥストラはかく語りき」「幻想交響曲」でもやりたい気分ですが(アホか)、そこはグっとこらえて地道に今やっている曲を楽しんでいこうと思います
見学のお問い合わせも増えてきて、5月も絶好調の防府ウィンドシンフォニーです
クラリネット奏者くんは「木管が来んのじゃ!」と嘆いてましたが、次回は木管楽器奏者の見学者さんにも来ていただけそうで楽しみです









